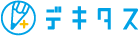Warning: Undefined array key "column_no" in /home/xs279430/johnan.jp/public_html/dekitus/column/clm10.php on line 87

勉強にご褒美をあたえることに賛成ですか?反対ですか?(その2)効果的なご褒美とは
コラム一発理解!PODCAST版
このコラムを音声で聞きたい方はコチラの動画をご覧ください。PODCAST版に要約して説明しています。
勉強におけるご褒美の効果的な活用方法とは
勉強のご褒美を与える方法は、子どもが学習に対して前向きな姿勢を持ち、学習習慣を身につけるために非常に有効です。しかし、ご褒美のタイミングや内容を適切に設定しないと、逆効果になることもあります。ここでは、勉強におけるご褒美の効果的な活用方法について詳しく見ていきます。
ご褒美を与えるタイミングは?
ご褒美を与えるタイミングは、子どものやる気を引き出すために非常に大切です。短期、中期、長期の目標ごとにご褒美を設定すると、効果的です。
まず、短期的な目標達成ごとに小さなご褒美を与えると良いでしょう。例えば、一週間の勉強計画を守った場合や特定の単元を終えたときに、ご褒美を与えると、次も頑張ろうという気持ちになります。
次に、中期的な目標を達成したときには、少し大きなご褒美を用意すると良いでしょう。例えば、月末にテストの点数が良かったり、計画通りに勉強できたりしたときにご褒美をあたえると、さらにやる気が出ます。
そして、長期的な目標を達成したときには、大きなご褒美を用意するのもよいでしょう。学期や学年が終わったときに、大きなご褒美を準備することで、継続的に頑張れるようになります。
ここで大切なのは、ご褒美をあげるタイミングを一定のルールにすることです。これにより、子どもは「頑張ればご褒美がもらえる」とわかって、もっとやる気を出します。また、勉強の進み具合を見えるようにすると、達成感を感じやすくなるので、カレンダーやグラフを使って記録するのも良いでしょう。
ご褒美は、「努力に対して」と「結果に対して」では、どちらが効果的?
結果に対するご褒美と努力に対するご褒美、どちらが効果的かという点については、子どもの性格や状況によって異なる場合も多いですが、一般的には以下のようなポイントを考慮するとよいでしょう。
努力に対するご褒美
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
結果に対するご褒美
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
大切なのはバランス
効果的なご褒美の与え方は、努力と結果の両方をバランスよく評価することです。例えば、毎日の勉強を頑張ったら小さなご褒美をあげると、子どもは日々の努力を続けやすくなります。また、テストや成績が良かったときには大きなご褒美をあげることで、子どもは具体的な目標達成に向けてモチベーションが高まります。
ご褒美にはどんな工夫が必要なの?
短期的な目標に対するご褒美
- 1時間集中して勉強した後: 集中して勉強することができたら、お菓子や小さな玩具などのご褒美を与える。
- 1つの単元を終えたとき: 単元ごとに区切りをつけ、達成感を感じさせるためにシールやスタンプを集めさせる。
短期的な目標に対してご褒美を設定することは、即効性があり、子どものモチベーションを高める効果があります。例えば、以下のようなタイミングでご褒美を与えるのも良いでしょう。
このように、短期的な目標に対するご褒美は、子どもが「ここまで頑張ればご褒美がもらえる」という具体的な目標を持つことで、集中力を維持しやすくなります。
長期的な目標に対するご褒美
- 1週間毎日勉強を続けたとき: 好きな本やおもちゃ、特別な外出など、大きめのご褒美を与える。
- 学期末や学年末に目標を達成したとき: 目標を達成したときには、特別なイベントや旅行などを計画する。
長期的なご褒美は、子どもが持続的に努力を続けるための動機付けになります。また、努力の積み重ねが大きな成果につながることを実感させることで、将来的な目標設定にも良い影響を与えます。
努力に対するご褒美
- 毎日少しずつ勉強を続けることを評価する: 勉強時間や学習量に応じて、ご褒美を設定する。
- 具体的な成果が出なくても、努力を褒める: 例えば、テストの点数が思わしくなかったとしても、勉強に取り組んだ姿勢を評価し、ご褒美を与える。
努力に対するご褒美は、子どもが結果に一喜一憂せず、日々の努力を大切にする態度を育むことができます。

ご褒美の内容と工夫
小さなご褒美
- お菓子、シール、スタンプ、小さな玩具など。これらは短期的な目標達成時に適しています。
大きなご褒美
- 好きな本、おもちゃ、外出、特別なイベントや旅行など。これらは長期的な目標達成時や、特に大きな努力をしたときに適しています。
ご褒美の内容は、子どもの興味や好みに合わせて工夫することが大切です。ご褒美が子どもにとって魅力的であればあるほど、学習へのモチベーションも高まります。
また、ご褒美の種類を定期的に変えることで、子どもの興味を維持し続けることができます。常に同じご褒美だと、次第に効果が薄れてしまうため、バリエーションを持たせることがポイントです。
ご褒美の与え方の工夫
ご褒美を与える際には、その与え方にも工夫が必要です。ただ単にご褒美を渡すだけでなく、努力や成果を具体的に認め、褒める言葉をかけることが大切です。
- 具体的なフィードバックを与える:「今日の勉強、よく集中して頑張ったね」といった具体的な行動を認める言葉を添える。
- ポジティブな言葉で褒める:「あなたの努力はすごいね」「この単元を終えたのは素晴らしいよ」といった肯定的な言葉を使う。
このように、具体的なフィードバックとポジティブな言葉を添えることで、子どもは自分の努力や成果がしっかりと認められていると感じ、自信を持つことができます。
ご褒美の効果を最大化するための注意点
- ご褒美の頻度とバランス: ご褒美があまりにも頻繁だと特別感が薄れ、逆にモチベーションが低下することがあります。適度な頻度で特別感を持たせることが重要です。
- 結果と努力のバランス: 結果だけでなく、努力を評価することで、子どもが結果に一喜一憂せず、日々の努力を大切にする態度を育むことができます。
- 個々の子どもに合わせた調整: 子どもによってモチベーションを感じるポイントは異なります。子どもの性格や興味をよく観察し、個別に調整することが大切です。
ご褒美を考えるのって結構大変・・・
勉強におけるご褒美の効果的な活用方法は、短期的な目標と長期的な目標のバランスを取り、結果だけでなく努力を評価することです。また、ご褒美の内容や与え方にも工夫を凝らし、子どもの学習意欲を高めることが重要です。これにより、子どもは学ぶことの楽しさや達成感を感じながら、持続的な学習習慣を身につけることができます。
確かにその通りですが、タイミングやご褒美の種類など、ご褒美を考えるの結構大変そうですね。
ご安心ください。デキタスなら親御さんに代わって、お子様にご褒美をあげちゃいます!
次回は、デキタスでは、どういうときにどんなご褒美がもらえるか詳しくご紹介します!